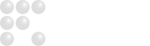企業のITインフラにおいて、仮想化技術の利用は一般的になりました。サーバーリソースの効率的な活用や運用管理の簡素化といったメリットがある一方、仮想マシンに集約されたデータをいかに保護するかという課題も重要です。本記事では、仮想マシンのバックアップがなぜ重要なのか、その基本的な仕組みから具体的な方法、そして最適なツールを選ぶためのポイントまで、分かりやすく解説します。
目次
仮想マシンにおけるバックアップの重要性
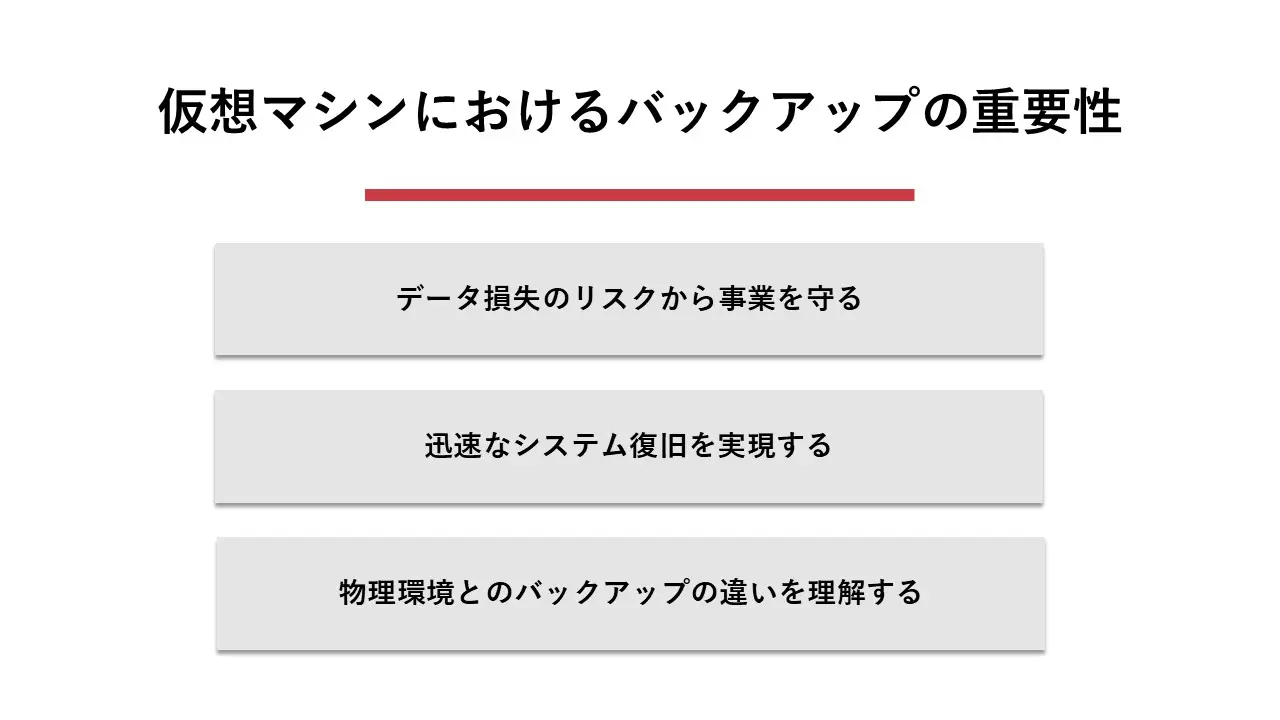
仮想マシン環境におけるバックアップは、物理サーバー環境と同様に、あるいはそれ以上に重要です。一つの物理サーバー上に複数の仮想マシンが集約されているため、障害が発生した際の影響範囲が大きくなる可能性があります。
データ損失のリスクから事業を守る
システム障害、人為的な操作ミス、サイバー攻撃など、データ損失のリスクは常に存在します。仮想マシン上の業務データや顧客情報が失われれば、事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。定期的なバックアップは、これらのリスクに対する最も基本的な防御策であり、企業の信頼性を維持するためにも不可欠です。
迅速なシステム復旧を実現する
万が一システム障害が発生した場合、事業への影響を最小限に抑えるためには、いかに迅速にシステムを復旧できるかが鍵となります。適切なバックアップがあれば、仮想マシン全体を障害発生前の正常な状態に復元できます。これにより、ダウンタイムを短縮し、機会損失を防ぐことが可能です。
物理環境とのバックアップの違いを理解する
物理環境のバックアップと仮想環境のバックアップでは、いくつかの違いがあります。仮想マシンはOSやアプリケーション、データがすべてファイル(仮想ディスクファイル)としてカプセル化されており、この特性を活かすことで、物理サーバーよりも効率的にマシン全体をバックアップできる手法が存在します。一方で、1台の物理ホストにリソースが集中するため、バックアップ処理が他の仮想マシンのパフォーマンスに影響を与えないよう配慮が必要です。
| 項目 | 物理環境 | 仮想環境 |
|---|---|---|
| バックアップ対象 | OS、アプリケーション、データを個別に、またはディスク全体 | 仮想ディスクファイルとしてマシン全体をカプセル化 |
| 復旧単位 | ファイル単位、またはOS全体の再構築 | ファイル単位、または仮想マシン全体の復元 |
| 効率性 | OSごとにエージェントが必要で管理が煩雑になることがある | ハイパーバイザーレベルでの統合バックアップが可能で効率的 |
| 課題 | ハードウェア依存性が高い | バックアップ時のホストリソース競合 |
仮想マシンバックアップの基本的な仕組み
仮想マシンのバックアップには、いくつかの基本的な考え方や技術が存在します。これらを理解することで、自社の環境に最適なバックアップ戦略を立てることができます。
スナップショット機能との違いは?
仮想化基盤には「スナップショット」という、ある時点の状態を保存する機能があります。これは一時的なバックアップとして便利ですが、本格的なバックアップの代替にはなりません。 スナップショットは元の仮想ディスクファイルへの差分情報として保存されるため、長期間保持するとパフォーマンスの低下を招いたり、管理が複雑になったりします。また、元のファイルが破損すればスナップショットからの復旧もできません。バックアップは、仮想マシンとは独立した場所にデータを複製・保管するものであり、根本的に役割が異なります。
オンラインバックアップとオフラインバックアップ
仮想マシンのバックアップは、対象の仮想マシンを稼働させたまま行う「オンラインバックアップ」と、停止させてから行う「オフラインバックアップ」に大別されます。現在では、業務への影響を避けるためにオンラインバックアップが主流です。 オンラインバックアップを実現するには、OSやアプリケーションが対応していることや、バックアップツールがVSS(Volume Shadow Copy Service)などの静止点作成機能と連携できることが重要です。
フルバックアップと差分・増分バックアップ
バックアップのデータ取得方法には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解し、バックアップ時間やストレージ容量の要件に応じて使い分けることが重要です。
| バックアップ方式 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| フルバックアップ | 対象の全データを毎回バックアップする方式。 | 復旧がシンプルで速い。 | バックアップ時間が長く、ストレージ容量を大量に消費する。 |
| 差分バックアップ | 前回のフルバックアップ以降に変更されたデータをバックアップする方式。 | フルバックアップより時間と容量を節約できる。復旧にはフルと差分の2つが必要。 | 回を重ねるごとにバックアップデータが肥大化する。 |
| 増分バックアップ | 前回のバックアップ(フルまたは増分)以降に変更されたデータをバックアップする方式。 | バックアップ時間とストレージ容量を最も節約できる。 | 復旧に手間がかかり、途中のデータが一つでも破損すると復旧できない。 |
「どの方法が自社に合うのか分からない…」という方は、まずは試してみるのがおすすめです。
詳しい資料や無料トライアルで、バックアップの違いを体感してみてください。
仮想マシンの主要なバックアップ方法
仮想マシンのバックアップを実現するためのアプローチは、主に3つに分類されます。それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、環境や要件に応じて選択する必要があります。
各仮想マシンにエージェントを導入する方法
物理サーバーのバックアップと同様に、各仮想マシンのOS内部にバックアップ用のソフトウェア(エージェント)をインストールする方法です。 この方法では、アプリケーション単位での詳細なデータ保護設定が可能ですが、仮想マシンの台数が増えるとエージェントの導入や管理の負荷が大きくなります。また、バックアップ処理が各仮想マシンのリソースを消費する点にも注意が必要です。
仮想化基盤(ハイパーバイザー)を利用する方法
VMwareのvStorage API for Data Protection (VADP) やHyper-VのVSSライター といった、仮想化基盤が提供するAPIを利用してバックアップを行う方法です。このアプローチは「エージェントレスバックアップ」とも呼ばれ、各仮想マシンにエージェントを導入する必要がありません。ホストサーバー側で処理を行うため、仮想マシンへの負荷を軽減し、効率的にバックアップを取得できるのが大きなメリットです。
ストレージ機能を利用したバックアップ
仮想マシンのデータを保存しているストレージ装置のスナップショット機能やレプリケーション機能を利用してバックアップを行う方法です。高速にバックアップを取得でき、サーバーへの負荷がほとんどないという利点があります。ただし、利用しているストレージ製品に依存する方法であり、別途ライセンスが必要になる場合があります。
主要な仮想化基盤ごとのバックアップ
現在、多くの企業で利用されている主要な仮想化基盤やクラウドサービスごとに、バックアップの考え方や特徴が異なります。
VMware vSphere環境のバックアップ
VMware vSphere環境では、VADPというAPIを利用したエージェントレスバックアップが一般的です。 VADPは、前回のバックアップから変更されたデータブロックのみを特定するCBT (Changed Block Tracking) という機能を備えており、これにより増分バックアップを高速に実行できます。多くのサードパーティ製バックアップツールがこのAPIに対応しており、効率的なデータ保護を実現しています。
Microsoft Hyper-V環境のバックアップ
Microsoft Hyper-V環境では、Windows Serverに標準搭載されているVSSフレームワークと連携してバックアップを行います。 DPM (Data Protection Manager) などのMicrosoft純正ツールや、多くのサードパーティ製ツールがHyper-Vのバックアップに対応しています。クラスター共有ボリューム (CSV) やSMB 3.0共有フォルダ上の仮想マシンも保護することが可能です。
クラウド(Azure VMなど)環境のバックアップ
Azureなどのパブリッククラウド上で稼働する仮想マシン(IaaS)もバックアップが不可欠です。Azure Backupのようなクラウドネイティブのバックアップサービスを利用することで、エージェントの管理をすることなく、ポリシーベースで簡単にバックアップを設定・自動化できます。 バックアップデータはクラウド事業者が管理する堅牢なストレージに保管されるため、高い可用性と耐久性が得られます。
仮想マシンバックアップツールの選定ポイント
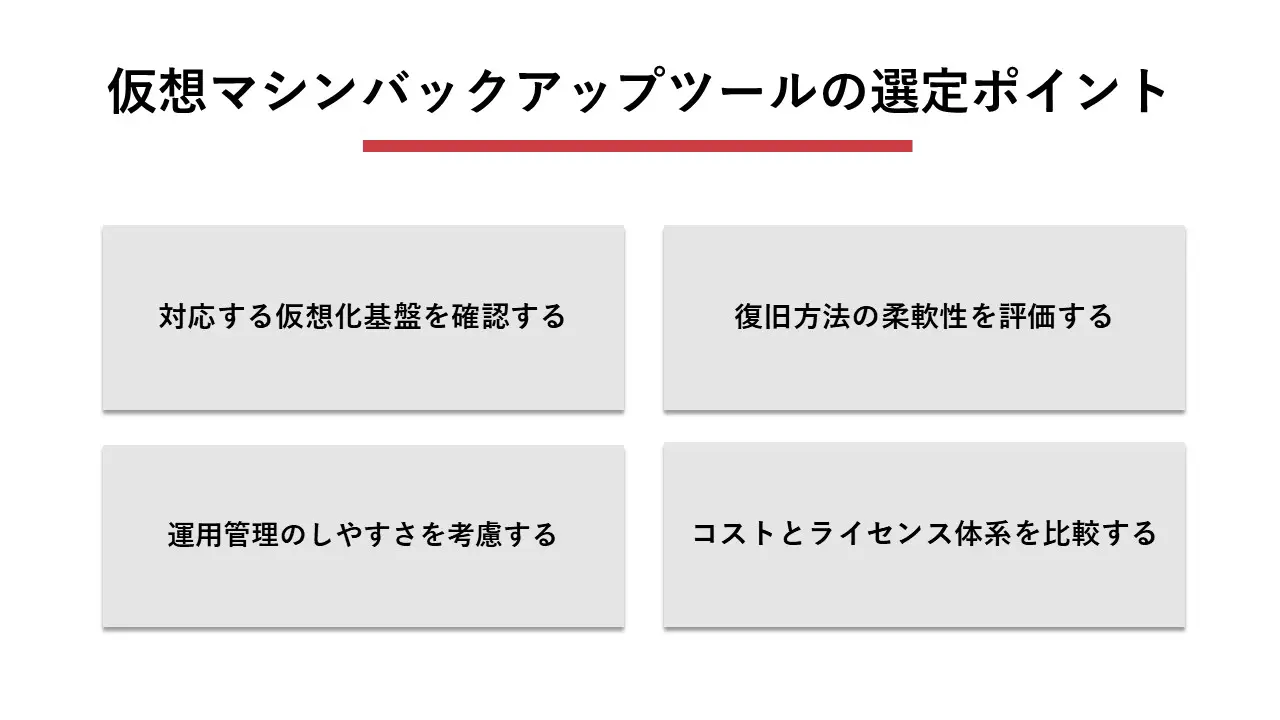
仮想マシンのバックアップを実現するためには、専用のバックアップツールを導入することが一般的です。ここでは、自社に最適なツールを選定するためのポイントを解説します。
対応する仮想化基盤を確認する
まず最も重要なのは、自社で利用している仮想化基盤(VMware, Hyper-V, KVMなど)にツールが正式に対応しているかを確認することです。 複数の仮想化基盤を併用している場合は、それらすべてを単一のツールで統合管理できる製品を選ぶと、運用がシンプルになります。
復旧方法の柔軟性を評価する
バックアップは復旧できて初めて意味を成します。ツール選定の際には、どのような復旧オプションが提供されているかを確認しましょう。仮想マシン全体の復旧だけでなく、特定のファイルやフォルダだけを迅速に取り出せる「ファイルレベルリストア」機能や、バックアップデータから直接仮想マシンを起動できる「インスタントリカバリ」機能の有無は、復旧時間(RTO)を短縮する上で非常に重要です。
運用管理のしやすさを考慮する
日々のバックアップ運用を効率的に行うためには、管理コンソールの使いやすさも重要な要素です。直感的なインターフェースでバックアップジョブの作成やスケジュール設定、リストア操作ができるかを確認しましょう。また、バックアップの成功・失敗を通知するレポート機能や、複数の拠点やクラウド環境を一元管理できるかも評価ポイントとなります。
コストとライセンス体系を比較する
バックアップツールのライセンス体系は、製品によって様々です。物理ホストのCPUソケット数に基づくもの、仮想マシンの台数に基づくもの、保護するデータ容量に基づくものなどがあります。自社の環境の規模や将来的な拡張計画を考慮し、最もコスト効率の良いライセンス体系の製品を選ぶことが大切です。
| 選定ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 対応仮想化基盤 | VMware, Hyper-Vなど、自社環境に対応しているか。複数環境の統合管理は可能か。 |
| 復旧機能 | VM全体のリストア、ファイル単位のリストア、インスタントリカバリなど、必要な機能が備わっているか。 |
| 運用管理性 | 管理コンソールの操作性、ジョブ設定の容易さ、レポート機能の充実度。 |
| ライセンス体系 | CPUソケット単位、VM単位、容量単位など。自社の規模に合った体系か |
仮想マシンバックアップにおける注意点
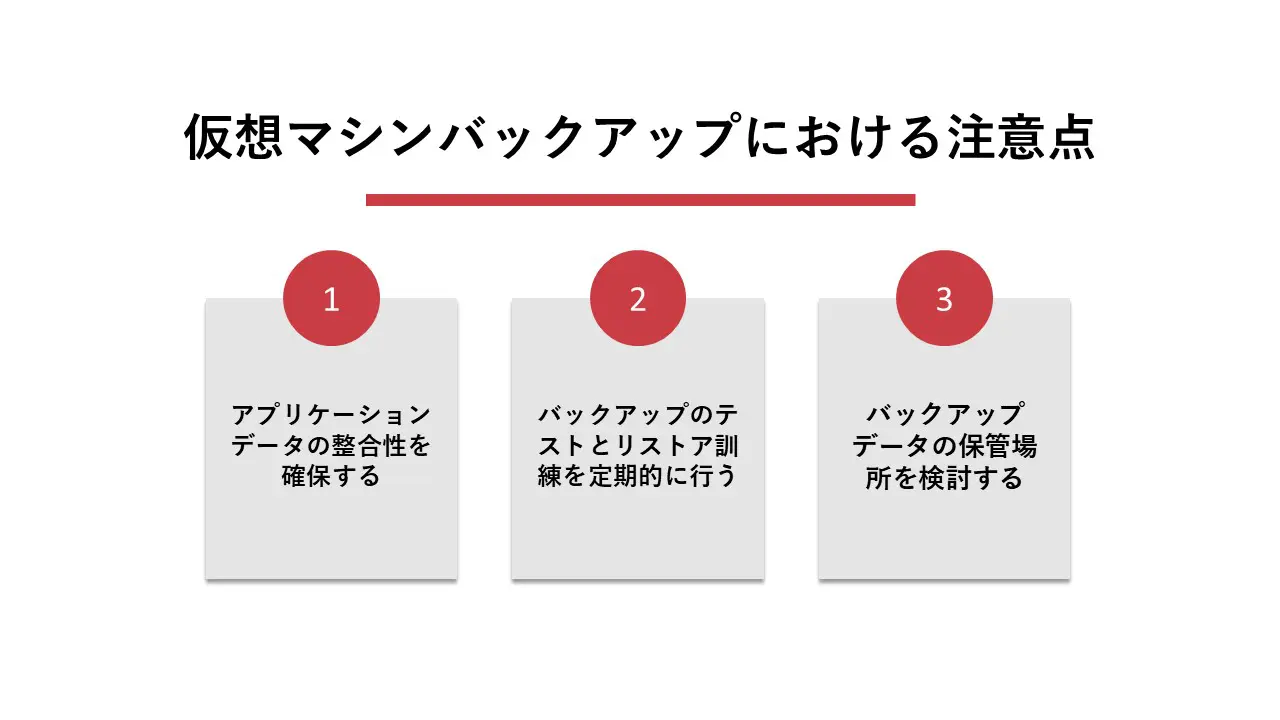
仮想マシンのバックアップを計画・運用する際には、いくつか注意すべき点があります。これらを怠ると、いざという時にデータを正常に復旧できない可能性があります。
アプリケーションデータの整合性を確保する
データベースサーバーやメールサーバーなど、常にデータの書き込みが発生している仮想マシンをバックアップする場合、データの整合性を確保することが極めて重要です。 バックアップツールがVSSなどと連携し、メモリ上のデータや処理中のトランザクションをディスクに書き込んでからバックアップを取得する「静止点」を作成できるかを確認する必要があります。これにより、アプリケーションレベルで一貫性のある、破損のないデータを保護できます。
バックアップのテストとリストア訓練を定期的に行う
バックアップは取得しているだけでは安心できません。「バックアップが正常に取得できているか」そして「そのバックアップから正常に復旧できるか」を定期的にテストすることが不可欠です。別の検証環境にリストアしてみるなどの訓練を計画に盛り込むことで、万が一の障害発生時にも慌てず、確実に対応できるようになります。
バックアップデータの保管場所を検討する
バックアップデータの保管場所は、元の仮想マシンが稼働している物理サーバーやストレージとは別の場所にすることが鉄則です。いわゆる「3-2-1ルール」(3つのデータコピーを、2種類の異なる媒体に、そのうち1つはオフサイトで保管)に従い、災害対策として遠隔地のデータセンターやクラウドストレージに二次保管することも検討しましょう。
まとめ
仮想マシンのバックアップは、現代のITインフラを支える上で欠かせない重要なプロセスです。その仕組みや手法は多岐にわたりますが、自社の環境や要件を正しく理解し、適切なツールと運用戦略を選択することが成功の鍵となります。本記事で解説したポイントを参考に、堅牢で信頼性の高いデータ保護体制を構築してください。
仮想環境にも対応したイメージバックアップソフトをお探しの方には、ActiveImage Protector -REがおすすめです。物理・仮想を問わず、シンプルな操作性で高速かつ効率的なバックアップを実現でき、ランサムウェア対策やシステム障害にも強みを発揮します。